「日本は超少子化国」、子育てに年間173万円必要
12月16日、政府は2005年版「少子化社会白書」を決定しました。2004年の合計特殊出生率が1.288と過去最低を更新した現状を踏まえ、日本を「超少子化国」と定義付けしました。
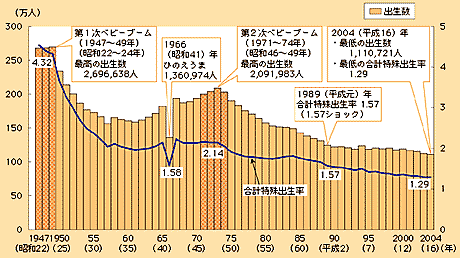
人口学上では、合計特殊出生率が1.3未満の国を「超少子化国」(lowest low fertility countries)としており、04年の出生率が03年の1.290を更に下回り、減少傾向に歯止めがかからないことから、この現象が一時的なものでないと判断しました。
また、子育てにどの程度の費用が掛かっているかを初めて試算しました。02年度の18歳未満の子育て費用は推計で総額38.5兆円に達し、内訳は教育費20.3兆円、生活費12.7兆円となっています。子ども1人当たりに換算すると年間173万円が必要としています。これに対し、国の児童・家族関係給付費は社会保障給付費全体の中で4%と少ないため、高齢者関係給付を見直し、子育てに対する公的支出の充実の必要性を訴えています。
 参考:「平成17年度少子化社会白書」内閣府のHPより
参考:「平成17年度少子化社会白書」内閣府のHPより
12月16日、政府は2005年版「少子化社会白書」を決定しました。2004年の合計特殊出生率が1.288と過去最低を更新した現状を踏まえ、日本を「超少子化国」と定義付けしました。
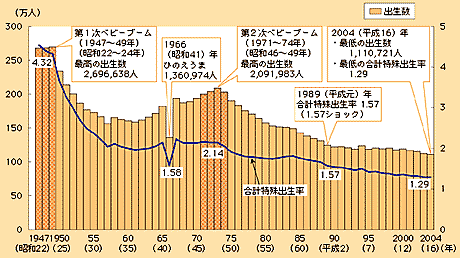
人口学上では、合計特殊出生率が1.3未満の国を「超少子化国」(lowest low fertility countries)としており、04年の出生率が03年の1.290を更に下回り、減少傾向に歯止めがかからないことから、この現象が一時的なものでないと判断しました。
また、子育てにどの程度の費用が掛かっているかを初めて試算しました。02年度の18歳未満の子育て費用は推計で総額38.5兆円に達し、内訳は教育費20.3兆円、生活費12.7兆円となっています。子ども1人当たりに換算すると年間173万円が必要としています。これに対し、国の児童・家族関係給付費は社会保障給付費全体の中で4%と少ないため、高齢者関係給付を見直し、子育てに対する公的支出の充実の必要性を訴えています。
 参考:「平成17年度少子化社会白書」内閣府のHPより
参考:「平成17年度少子化社会白書」内閣府のHPより諸外国や自治体の支援実例を紹介
05年版「少子化白書」では、「社会全体で若い世代や子育て世帯を支援することにより、少子化の流れを変えていかなければならない」と明示した。昨年の初の白書では理念的に支援の必要性を説いたが、2回目になる05年版は企業や地方自治体、さらに諸外国における子育て支援策の紹介に紙数の大半を割き、具体的な実例を数多く掲載しています。すでに人口動態調査の推計値で、05年にも人口増がマイナスに転じた現実の前に、少子化対策に、あれかこれと逡巡する時期は過ぎました。内外の事例を参考に、必要とされる政策を総動員すべき時であることを改めて肝に銘じたいと思います。
まず、注目されるのは、諸外国、特に少子化の“先輩”である欧米諸国の施策を詳細に伝えていることです。欧米諸国は1970年代から80年代にかけて出生率が大きく低下しました。積極的に支援策を打ち出したスウェーデン、フランスなどは90年代に入り明らかに出生率が回復・高めで推移しています。
その柱は、いずれも(1)育児休業を取りやすくし、保育サービスを充実することで家庭と仕事を両立できるようにした(2)児童手当や税制による経済的支援の充実の2点です。特にフランスでは、30種類もの手当を支給、その6割を企業からの拠出金で支え、そのほかを一般社会税と呼ばれる目的税と国庫支出で補うなど幅広い社会的な負担を財源としています。
欧米諸国の特徴の一つは、支援策の目的を「少子化対策」とはしていない点にあります。子どもやその家族に対して支援する「児童・家族政策」として位置づけ、「働きやすい」「子育てしやすい」環境の整備が、結果的に出生率の改善につながっています。
一方、国内の現状では、子育て期にある30歳代の男性の4人に1人は週60時間以上仕事をしていると、白書は指摘しています。その結果、家庭と子どもに向き合う時間を十分に持てず、依然として、子育ての負担が女性に集中しています。仕事のキャリアを積み上げていこうとする女性にとって、この事実は大きな障害になっています。女性に限らず、男性にとっても家庭と仕事を両立できるような仕組みが求められています。白書は「毎日がNO残業デー」を掲げたり、育児期間の在宅勤務を認めたり、事業所内に託児所を設置した事例などを紹介しています。
地方自治体について白書は、あえて自治体独自の事業や、国の基準以上の施策である、いわゆる「上乗せ事業」に言及しています。保育と乳幼児医療費の助成に対する上乗せが大半で、東京都の認証保育所制度、江戸川区の保育ママ事業などが効果的な手法として紹介され、乳幼児医療費助成については全都道府県の比較まで行っています。
次代を担う子どもたちとその家族に対する支援は、その社会のより良い将来を支えます。この共通認識を日本でも築き上げなければなりません。そのために、国・地方自治体に限らず、企業や地域社会などすべての分野での協力と役割分担が欠かせません。
05年版「少子化白書」では、「社会全体で若い世代や子育て世帯を支援することにより、少子化の流れを変えていかなければならない」と明示した。昨年の初の白書では理念的に支援の必要性を説いたが、2回目になる05年版は企業や地方自治体、さらに諸外国における子育て支援策の紹介に紙数の大半を割き、具体的な実例を数多く掲載しています。すでに人口動態調査の推計値で、05年にも人口増がマイナスに転じた現実の前に、少子化対策に、あれかこれと逡巡する時期は過ぎました。内外の事例を参考に、必要とされる政策を総動員すべき時であることを改めて肝に銘じたいと思います。
まず、注目されるのは、諸外国、特に少子化の“先輩”である欧米諸国の施策を詳細に伝えていることです。欧米諸国は1970年代から80年代にかけて出生率が大きく低下しました。積極的に支援策を打ち出したスウェーデン、フランスなどは90年代に入り明らかに出生率が回復・高めで推移しています。
その柱は、いずれも(1)育児休業を取りやすくし、保育サービスを充実することで家庭と仕事を両立できるようにした(2)児童手当や税制による経済的支援の充実の2点です。特にフランスでは、30種類もの手当を支給、その6割を企業からの拠出金で支え、そのほかを一般社会税と呼ばれる目的税と国庫支出で補うなど幅広い社会的な負担を財源としています。
欧米諸国の特徴の一つは、支援策の目的を「少子化対策」とはしていない点にあります。子どもやその家族に対して支援する「児童・家族政策」として位置づけ、「働きやすい」「子育てしやすい」環境の整備が、結果的に出生率の改善につながっています。
一方、国内の現状では、子育て期にある30歳代の男性の4人に1人は週60時間以上仕事をしていると、白書は指摘しています。その結果、家庭と子どもに向き合う時間を十分に持てず、依然として、子育ての負担が女性に集中しています。仕事のキャリアを積み上げていこうとする女性にとって、この事実は大きな障害になっています。女性に限らず、男性にとっても家庭と仕事を両立できるような仕組みが求められています。白書は「毎日がNO残業デー」を掲げたり、育児期間の在宅勤務を認めたり、事業所内に託児所を設置した事例などを紹介しています。
地方自治体について白書は、あえて自治体独自の事業や、国の基準以上の施策である、いわゆる「上乗せ事業」に言及しています。保育と乳幼児医療費の助成に対する上乗せが大半で、東京都の認証保育所制度、江戸川区の保育ママ事業などが効果的な手法として紹介され、乳幼児医療費助成については全都道府県の比較まで行っています。
次代を担う子どもたちとその家族に対する支援は、その社会のより良い将来を支えます。この共通認識を日本でも築き上げなければなりません。そのために、国・地方自治体に限らず、企業や地域社会などすべての分野での協力と役割分担が欠かせません。












