妊娠中に脳内出血を起こした東京都内の女性が、都立墨東病院など7病院に受け入れを断られた後に死亡するという事件が10月4日起こりました。
女性はまず、かかりつけの産婦人科医院に救急車で運ばれました。その医院では医師が命に関わる重篤な事態だと判断して高次機能を持った病院に受け入れを頼んだのですが、7つの病院に断られました。最終的に救命設備の整った病院に運び込まれたのは、夫が妻の異常に気づいてから、おそらく2時間近くがたっていたと思われます。最初に女性が運び込まれたかかりつけの産婦人科医院から受け入れ先の都立墨東病院までは10分とかからない距離なのにです。
医療施設が充実しているはずの東京でなぜこんなことが起こるのか?
通常、妊娠した女性は地域の産婦人科医院で検診を受け、とくに問題がない限り、出産まで一貫してその病院でお世話になります。しかし、危険度の高い出産となる場合は「総合周産期母子医療センター」という施設があり、そこでリスクの高い妊娠に対する医療と高度な新生児医療を受けることができるシステムになっています。
総合周産期母子医療センターは全国45都道府県に74施設あり、そのうち東京には9つの施設があります。(2008年5月現在)
土日祝日の産科救急の受け入れが不可能だった墨東病院
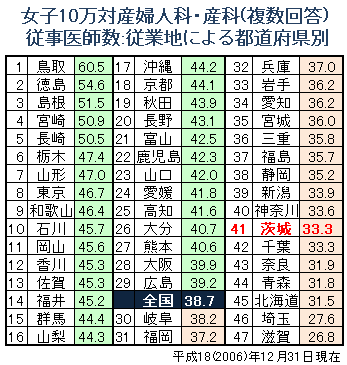 今回、脳内出血を起こした妊婦を受け入れた都立墨東病院は、東京に9つある総合周産期母子医療センターでした。周産期母子医療センターには常時2名の産科医がいるように決められているのですが、墨東病院では6月に1人の産科医が退職してしまい補充ができていない状態でした。
今回、脳内出血を起こした妊婦を受け入れた都立墨東病院は、東京に9つある総合周産期母子医療センターでした。周産期母子医療センターには常時2名の産科医がいるように決められているのですが、墨東病院では6月に1人の産科医が退職してしまい補充ができていない状態でした。
そのためこの病院では土日や祝日の産科救急の受け入れが不可能な状態だったのです。
このため、最初に受け入れを打診された墨東病院はいったん受け入れできないと回答します。その後、かかりつけの産婦人科医院の医師は、いくつもの病院に受け入れを依頼しますが、すべて断られ、再度、墨東病院に連絡をしました。墨東病院は急遽、産科部長に登院を要請し、妊婦を受け入れました。墨東病院側もその間、何もしなかったわけではありません。知り合いの病院に連絡し、妊婦の受け入れを頼んでいます。
この件に関わった医療関係者が救命のための努力を怠ったとは思えません。現時点では、受け入れが遅れたこととの因果関係も証明されているわけではありません。しかし遺族とすれば、もう少し早く診てもらえたらという思いはあるでしょう。結果的に妊婦さんを救えなかったことにやりきれない思いが残ります。
“たらい回し”は東京の方が多いという現実
2006年の総務省調べでは、救急の妊婦さんが受け入れを10回以上断られた件数を見ると、東京は30件もあるのに対し、千葉県では6件、大阪では4件と、東京が飛び抜けて多いことが分かります。この原因として考えられるのは、地方では高次機能を持った病院が1カ所か2カ所ぐらいしかないのに対して、東京ではいくつもあるためと考えられます。地方では連絡があればとにかく自分のところが受け入れるしかないのですが、東京では救命施設がいくつもあるので、自分のところが断ってもよそが受け入れてくれるだろうという意識があるのだと思われます。
東京では受け入れまでに最大217分、27回もさまざまな病院に電話をしてやっと受け入れてもらったという例も報告されています。
女性はまず、かかりつけの産婦人科医院に救急車で運ばれました。その医院では医師が命に関わる重篤な事態だと判断して高次機能を持った病院に受け入れを頼んだのですが、7つの病院に断られました。最終的に救命設備の整った病院に運び込まれたのは、夫が妻の異常に気づいてから、おそらく2時間近くがたっていたと思われます。最初に女性が運び込まれたかかりつけの産婦人科医院から受け入れ先の都立墨東病院までは10分とかからない距離なのにです。
医療施設が充実しているはずの東京でなぜこんなことが起こるのか?
通常、妊娠した女性は地域の産婦人科医院で検診を受け、とくに問題がない限り、出産まで一貫してその病院でお世話になります。しかし、危険度の高い出産となる場合は「総合周産期母子医療センター」という施設があり、そこでリスクの高い妊娠に対する医療と高度な新生児医療を受けることができるシステムになっています。
総合周産期母子医療センターは全国45都道府県に74施設あり、そのうち東京には9つの施設があります。(2008年5月現在)
土日祝日の産科救急の受け入れが不可能だった墨東病院
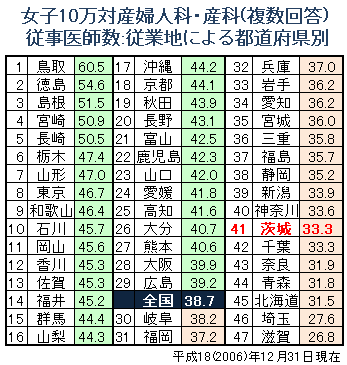 今回、脳内出血を起こした妊婦を受け入れた都立墨東病院は、東京に9つある総合周産期母子医療センターでした。周産期母子医療センターには常時2名の産科医がいるように決められているのですが、墨東病院では6月に1人の産科医が退職してしまい補充ができていない状態でした。
今回、脳内出血を起こした妊婦を受け入れた都立墨東病院は、東京に9つある総合周産期母子医療センターでした。周産期母子医療センターには常時2名の産科医がいるように決められているのですが、墨東病院では6月に1人の産科医が退職してしまい補充ができていない状態でした。そのためこの病院では土日や祝日の産科救急の受け入れが不可能な状態だったのです。
このため、最初に受け入れを打診された墨東病院はいったん受け入れできないと回答します。その後、かかりつけの産婦人科医院の医師は、いくつもの病院に受け入れを依頼しますが、すべて断られ、再度、墨東病院に連絡をしました。墨東病院は急遽、産科部長に登院を要請し、妊婦を受け入れました。墨東病院側もその間、何もしなかったわけではありません。知り合いの病院に連絡し、妊婦の受け入れを頼んでいます。
この件に関わった医療関係者が救命のための努力を怠ったとは思えません。現時点では、受け入れが遅れたこととの因果関係も証明されているわけではありません。しかし遺族とすれば、もう少し早く診てもらえたらという思いはあるでしょう。結果的に妊婦さんを救えなかったことにやりきれない思いが残ります。
“たらい回し”は東京の方が多いという現実
2006年の総務省調べでは、救急の妊婦さんが受け入れを10回以上断られた件数を見ると、東京は30件もあるのに対し、千葉県では6件、大阪では4件と、東京が飛び抜けて多いことが分かります。この原因として考えられるのは、地方では高次機能を持った病院が1カ所か2カ所ぐらいしかないのに対して、東京ではいくつもあるためと考えられます。地方では連絡があればとにかく自分のところが受け入れるしかないのですが、東京では救命施設がいくつもあるので、自分のところが断ってもよそが受け入れてくれるだろうという意識があるのだと思われます。
東京では受け入れまでに最大217分、27回もさまざまな病院に電話をしてやっと受け入れてもらったという例も報告されています。
“たらい回し”どころではない。地方ではより深刻な状況に
先の日製日立総合病院の記事でも述べた通り、茨城県の県北地域では産婦人科救急の体制自体が崩壊の危機を迎えています。来年度、日製日立総合病院は、地域周産期母子医療センターの指定を返上せざるを得なくなります。東大病院以外から産婦人科医を確保することに全力を挙げますが、毎日の当直医を擁する体制維持は非常に困難です。
こうした産婦人科救急の空白地帯が全国に広がっています。
安心して子どもが産める社会を
出産に伴って、妊婦が危険な状態になるということは、まれなことではありません。近年では高齢出産も増えており、その場合の危険も増えています。もし妊婦が危険な状態になったときの搬送体制、受け入れ病院と医師の確保など、解決しなければならない問題はたくさんあります。
複数の病院がある大都市でも、「自分のところで引き受けなければ」、という当事者意識を高めていくことが必要です。
地方を中心に広がる産婦人科不足を解消する施策も求められています。
緊急的には産婦人科、特に出産にかかわる診療報酬を引き上げることが必要です。妊婦への負担増は、「出産一時金」の大幅拡充で補うべきです。さらに、休職中の女性産婦人科医の現場復帰を進めるべきです。先日の日製日立総合病院の岡裕爾先生からの意見交換でも同様の提案をいただきました。
安心して子どもが産める社会を作るためには、産婦人科の充実は、少子化の流れの中で、最優先の課題になっています。
先の日製日立総合病院の記事でも述べた通り、茨城県の県北地域では産婦人科救急の体制自体が崩壊の危機を迎えています。来年度、日製日立総合病院は、地域周産期母子医療センターの指定を返上せざるを得なくなります。東大病院以外から産婦人科医を確保することに全力を挙げますが、毎日の当直医を擁する体制維持は非常に困難です。
こうした産婦人科救急の空白地帯が全国に広がっています。
安心して子どもが産める社会を
出産に伴って、妊婦が危険な状態になるということは、まれなことではありません。近年では高齢出産も増えており、その場合の危険も増えています。もし妊婦が危険な状態になったときの搬送体制、受け入れ病院と医師の確保など、解決しなければならない問題はたくさんあります。
複数の病院がある大都市でも、「自分のところで引き受けなければ」、という当事者意識を高めていくことが必要です。
地方を中心に広がる産婦人科不足を解消する施策も求められています。
緊急的には産婦人科、特に出産にかかわる診療報酬を引き上げることが必要です。妊婦への負担増は、「出産一時金」の大幅拡充で補うべきです。さらに、休職中の女性産婦人科医の現場復帰を進めるべきです。先日の日製日立総合病院の岡裕爾先生からの意見交換でも同様の提案をいただきました。
安心して子どもが産める社会を作るためには、産婦人科の充実は、少子化の流れの中で、最優先の課題になっています。
当直1人、県内の総合周産期センターも
茨城新聞(2008/10/26)
妊婦受け入れ拒否で県が確認
病院に相次いで受け入れを断られた妊婦が「総合周産期母子医療センター」に指定されている東京都立墨東病院で出産後に死亡した問題で、県内の同センター三カ所を県が確認したところ、県内でも墨東病院と同様、当直医が一人になる場合があることが二十六日までに分かった。ただ、墨東病院のように、研修医一人で当直をするケースはなかった。県は「本県ではセンターが中心となって受け入れ先を探すことになっている。東京のような事態は生じにくいのではないか」としているが、深刻な医師不足により、現状の周産期医療体制が継続困難になる可能性もある。
県医療対策課によると、高度医療に対応する県内の総合周産期母子医療センターは▽水戸済生会総合病院・県立こども病院(県央・県北ブロック)▽土浦協同病院(県南・鹿行ブロック)▽筑波大付属病院(つくば・県西ブロック)の三ブロック体制。これに準じた「地域周産期母子医療センター」として日立製作所日立総合病院(県北サブブロック)などを指定している。
各センターの産科常勤医は水戸済生会六人、土浦協同八人、筑波大十一人(婦人科含む)。筑波大以外は当直が一人になることもあるが、一人で対応できないときはもう一人を呼び出す体制にするとともに、研修医の場合は必ず常勤医と組んで二人体制で当直に就いている。
全国的な医師不足は県内にも影響を与え、日製日立病院では医師確保の見通しが立たず来年四月以降の分娩(ぶんべん)予約を休止。産科常勤医も四人に減った。
同病院など地域の中核病院が産科を継続できなくなると県内全体の周産期医療体制が崩壊しかねない。県医療対策課は「産科、小児科の医師不足は特に深刻。もはやお金を出せば解決できる問題ではなく、県民が知恵を出し合って乗り切らないとならない段階に来ている」としている。
東京で死亡した妊婦(36)は十月四日、かかりつけの産婦人科医から連絡を受けた都立墨東病院(墨田区)など八カ所の病院に診療を断られ、最終的に墨東病院で出産後、脳内出血の手術を受けたが三日後に死亡した。墨東病院は産科の常勤医が四人しかおらず、当日の当直は研修医一人だけだった。
今年三月に総務省消防庁がまとめた妊婦などの救急搬送状況によると、搬送を三回以上断られた妊婦の割合は昨年、全国平均で4・8%。東京、神奈川、大阪など大都市圏を中心に七都府県がこの割合を上回り、本県も6・4%と全国平均を上回った。二〇〇四年の全国平均1・9%と比べ、割合は三年ほどで二・五倍になり、妊婦の「たらい回し」も深刻化している。












